 |
| 新聞紙上に展開した楢山佐渡論 1 「楢山佐渡」1 半白老人 |
| 目次 半白老人(鈴木 巌) 岩手日報紙上(自明治41年10月14日、至11月1日) 刎首の刑に処された楢山佐渡の生涯を紹介。方向を過ったが古武士であったとする佐渡論を展開する。但し、舊暦散人が「半白老人の楢山佐渡と濤庵迂人批評とを併せてこれを読む」、「濤庵先生の再び佐渡を論ずる」といふ一篇に就てで指摘するように誤伝も散見する。 濤庵迂人(波岡茂樹) 同紙上(自明治41年11月7日、至11月10日) 楽しく読ませもらったと半白老人への謝辞を述べつつ、佐渡は京師で何を見て来たのかと疑問を呈し、大局に通じない典型。目時隆之進の出奔、中島源蔵の憤死に至っても責任を感じない人物。佐渡は古武士に値しないとした反論を展開す。11月12日附で半白老人より答礼謝辞あり(ここでは割愛) 舊暦散人(谷河尚忠) 同紙上(自明治41年12月16日、至12月19日) 半白老人、特に濤庵迂人の佐渡履歴記述に誤伝を一節、一節指摘し、史実を曲げているとした批判を展開する 濤庵迂人 同紙上(自明治42年3月1日カ、至3月25日) 舊暦散人の指摘に誘導されて奥羽越列藩同盟について、大義名分論に及び濤庵迂人の見解がある。「吾人の蒐集した頗る豊富ならざる(意味不明)史料を基礎としての佐渡に関する評論」とするが、舊暦散人の指摘に耐え得る応答のための史料は乏しく、戦場となった鹿角口、雫石口、および秋田領内の久保田、生保内、横手等の地理感が欠如しているなど、全く説得力は窺えない。 舊暦散人 同紙上(自明治42年3月28日至5月8日) 自分はその時代を生き抜いて来た生き証人(文中の履歴を参照)として、楢山佐渡を語り、盛岡藩の奥羽同盟の意義を記述する。 楢山佐渡半白老人(鈴木 巌)(一) 楢山佐渡は武士の代表的人物であった。彼が六歳御相手として初めて召し出されて以来、明治二年六月二十九日にして一藩上下の責めを一身に引き受け、報恩寺に刎首せらるゝまでの間の言動に徹してみれば、渾身さながら武士道で打ち固めたるごとく、武士としての彼れ自然にこれを具有して居ったやうに思はれた。彼は身の丈六尺あまり、中肉にして白色の美男子ですこぶる真面目に両手を拳に握り、ゆらりユラリと行くさまはなかなかに立派で、國老としての風采はおのづと人に畏敬せられるのであった。平生外和にして内甚だ剛、当節でいへば殆ど融通の利かぬ男と見られそうな人物であった。彼の家は元と藩公の分系にして、父の帯刀に至るまで世々藩の重役に列したのである。故に佐渡たるもの彼がごとき人傑たらざるも、少くも御加判役の伴食たらんことは固より予期し得られたのである。然るに栴檀の二葉たる、年少の五左衛門(佐渡の幼名)は望みの是処にあらずして、御加判役たるは望ましくない、何処か代官となって御奉公を励みたいとは、彼が口にする所の希望であった。 顧みるに、当時代官政治の腐敗せる事情は彼は疾くに看破して、先づ地方の情弊を矯め、藩政の基礎を鞏固にして、それから徐に中央で総括りをしやうといふ考えであったのであろう。彼はこの時からして最早名誉ある栄職を伴職として甘んずべき積もりではなかった。家格の名に満足せずして、実績を身に行うとしたのである。彼は天保十一年の出生で存命であれば当年は七十八歳になる。さうして帯刀の正室の子ではなかった。正室は小八戸、例の幕府大老の面前で藩公の御墨付を食ひ破って田名部五千石を恢復した小八戸のアトから嫁ぎ来たった人で、なかなかの賢夫人であった。然るに不幸にしてこの夫人に子がなく甚だ遺憾のことに思はれて、自ら栗谷川某女を撰択しこれを推薦して帯刀の妾たらしめた。佐渡は則ちこの妾腹に出たのであるが、佐渡はこの場合は腹は真の借り物で、生れ落ちて以来佐渡の教育は専らこの賢夫人の手に引き受けられた。則ち五左衛門はこの賢夫人に鍛えられて武士の手本といはるゝ佐渡となったのである。彼と戸田一心流長嶺七之丞に同門であった老人の言によりいへば、無論自宅に師範を招きて指南を受くべきであるのに、佐渡は常に伴をつれて自ら通学していた。而して師弟や同門の礼を守る事など甚だ固く、例へば水を使ふにも決して他人の汲んであるものものを用ひなかった。伴にも命ぜずに必ず自身に汲んで来るような男であった。家格は家格なり人物も人物であるから相手になるものもタマには諂って八百長をやらかすことがある。さういふ場合には佐渡は頗る不機嫌で、勝負は兎も角と武士の面目に関することなりとして甚だ喜ばなかった。 (二) 佐渡は十五で側詰となり、二十二で國老に抜擢されたのである。たとへ家柄は家柄でも時勢が時勢でも國老が勤まるとはたしかに凡物てない証拠である。國老拝命の発表せらるるや、菓子折だとか鰹魚節だとか種々雑多の御祝ひが先きを争ふて玄関に到来する。佐渡はこれを尋常に受け、一々名札を附けて八畳敷一杯に積み重ねた。いよいよこれで来るものもないといふ日になってか、篤く礼を述べて悉くこれを銘々に返却したという話しである。無論潔白には相違ないが、随分人のよくないやり方とも思はれる。その頃である。例の野田の一揆がしばしば起こって、迂回して遠野からやって来る。南部土佐出張して頻りに諭すところあったけれど、なかなか承服しない。手にあまして施すべき術もなかったので、佐渡は自ら鎮撫の任に当らんとし且つ利済侯に求むるに、幸にして功を奏するを得るに至らば、藩政を挙げて己れに一任せられんことを以てした。佐渡は一揆の起れる原因を看破して、その根底から洗ひあげて禍根を抜き去らうとしたのである。然るに佐渡は傑物たるに相違なからんも彼は弱輩である。利済侯の眼中にはいまだ藩政を挙げて委任すべき器とは映じて居なかった。青臭いとでも感じ取られたであろう。不幸佐渡は遂に利済侯の逆鱗に触れて閉門を命ぜられ、退いて謹慎して居らねばならぬことになった。然るに一揆は尚ほ鎮静いたらず、一団の後ろに控えたる一隊は、席の旗の向きさきを転じて気仙から仙台領に這入ったのである。これは実に由々しき一大事で、信濃守利済侯の運命はこの席の旗の御領の於境を越ゆる分秒の時間に繋って居ったのである。仙台侯は一揆の申立てを取り上げて、遂に委曲の事情を幕府に申出られた。わが南部家よりはしばしば仙台に交渉して、徒党の引渡しを要求するけれど、伊達家では容易に承諾しない。遂に罪人としないといふ条件を附して談判ようやく整ひ水沢まで送り届けられて引き渡しを得たのであった。既に仙台から申出でのありたる以上、幕府における首尾のよからざるはいふまでもないから、取りあえず重臣の内より上京せしむることとなって、いろいろ詮議を尽くして人選して見たのであるが、差し当たり佐渡を措て適任の人物がない。そこで佐渡の閉門を解き、直に上京せしむるといふ命令が下ったのである。彼れ斯るお家の一大事と合っては、固より傍観し得られべきながら、命を奉じて江戸に至り、兎も角も加州侯へと参上して見たが、侯は事面倒と見て取られたか面会を謝絶された。然るに加州邸に心利きたる女中あり、侯の内意を含みてか、窃かに佐渡に注意して斯様引き続き百姓一揆の起こるがごとき御事情ではお家の一大事、コトによってはお國替えの御沙汰あらんことも図られず、この場合はよろしく信濃守御自身にお上ぼりあって、その向きの御首尾を取繕はるゝがよからんと申しかばね佐渡も余儀無きことに思ひ更に芸州侯にいたりたるも侯も同様面会を許し給はず、且つ内々同じやうの御心付けもあり、宇和島侯のごときは、直きに御会ひあって、是処でも利済侯の上京を促がされたれば、流石の佐渡も彼れ単独の力に及び兼ねて残念ながら一先ず帰盛することになった。 (三) 佐渡は兎も角も一旦帰盛はしたものゝ、幕府の首尾は自身の力に及び兼ぬる案外の雲行きであったので、一つには彼は元来持ち前の剛直を数次君側にやり損ねて、利済侯の御覚え実は甚だ目出たからず、殊に漸く閉門御免の御沙汰を蒙ってまだ幾らも日数の経たぬ際でもあり、たとひ芸州(安芸広島・浅野家)、加州(加賀金沢・前田家)、宇和島(伊豫宇和島・伊達家)諸侯の御注意ありと申出なればとて、然らばと直ぐに御上京仰せ出されべきやうにも思はれず、彼れ是れ心がありて、平生多弁ならざる彼れ佐渡は、帰盛この方閉じ籠り居て、何か物案じ顔に不愉快の様子に見へたので、帯刀夫婦も更にその真相が解けず、これよりさきに、両親の計ひに妻を迎ふる内議もありたれば、斯る取に婚礼を行ふて、妻たるものを迎ひ取らば、結ばるゝ心の解けることもあらんとて、取り急ぎ式を挙げたれど、彼は依然として喜べる色になく、おまけに折角迎ひ取りたる花嫁と室を同臥せずといふ変な事をするので、帯刀夫婦も更に心配をまし、生母を以て説を諭さしめたれど、唯だお前達の知ったことではないと笑って応ぜぬので、一同困り果てゝ居りたるに、かねて気に入の家来澤田長左衛門は、心利きたる積りにて、或る夜佐渡の居間に花嫁を導きゆき、佐渡へいふやう、旦那さまお前さまは男でも奥さまを貰ったワケでもあるまいし、何たってヘンなことをなさるんです、と自ら夜のものを述べ、先づ花嫁を臥さしめて、佐渡の手を取りイザ花嫁の傍らへと引かんと世子に、彼は怒りもせず、ウンさうかとアベコベに長左衛門の利き腕取って花嫁の夜具に押し込、長左衛門よろしく頼むと平気に机に向かって読書をし居るので、流石の長左衛門もあまりの事に呆気に取られ、眼キョロキョロ、赤くなり青くなって逃げ出したといふ奇談もある佐渡が、いよいよ決心して霊承院殿に拝謁のため、熟慮の上にも熟慮を重ね、深く自ら決心して霊承院殿(利済の法号)に拝謁のために途上したのは、長左衛門の茶番狂言のその翌くる日出合った。彼は熟慮の上に熟慮を重ね、深く自ら決する所あって密かに白装束を下に着服し、立会のためにと東中務に同席を求めて、その御覚ええの目出たからざる君利済侯の御面前にピタリと坐り込んだ、もとより主家の一大事お国の安危に関するのであるから、彼は懸命ナノである。一揆の起りから、お政事向ききの欠点、非ぬ風評の江戸に達し居るのみか、仙台からの申出によって幕府の首尾ますます宜しからず、加州・芸州・宇和島諸侯の御配慮の点から、事細々と利害を説きて、今日の場合は、君御自身御出府あって御取り繕ひこれなきにおいては、御家ノ一大事、南部一版の浮沈安危に関すと退引き鳴らず、論じ詰めつめ、さて御意如何にと伺ひ出たるに、流石の利済侯、甚だ穏やかなら図、御不機嫌であったが理につめられてはイヤとは申されず、左様のわけならば上ることにしやうと仰せ出されたれば、佐渡は有難き仰せと喜び勇み、またも御意の変らぬ間にと、直に御伴の人数など仰せ出され、すかさず 準備も整ひい、江戸に向けて信濃守様(利済の官名)御出発といふことにまで運ばれたのである。 (四) この度の御上京は、信濃守殿御自身に思ひ立たれたる次第にてはこれなく、全く佐渡が忠言の理につめられていやいやながらの御決心に出でられたることなれば御道中も更にはかとらせ給はず、御出発のその当日は仙北町の徳田屋といふに先づ御一泊といふ体裁で、イカなこと、何んぼ汽車のなかった昔なればとて、江戸まで 三十何日を要せられたといふことである。寧ろ滑稽な道中を試みられたのであるが、利済侯の御心になって見れば、後ろ髪の引かるゝも御尤も千万御心底を恐察し居れる佐渡がこの御有り様を見つゝ、御機嫌をそこねまじと長道中に心血を注ぎて漸く着京したるその時の彼れ佐渡が顔色は如何にも窶れて何時も元気の佐渡とは似ても似つかぬ疲労の体であったので、在京の戸来勘左衛門は一と目見るなり、モノをもいはず先づ彼を臥床に誘ふて安眠せしめたが、佐渡も寝たは寝たり、二日二た晩ぶっ通し寝過ごしたといふことである。アトで佐渡が若しも彼の時勘左衛門が好意なくば、大事の御用も満足に勤まらなかったであろうと人に話したこと、左もあるべきである。斯くて信濃守着京のこと公義にて届出でられたれば、御大老阿部伊勢守より一門のもの出頭するやうにと達しがあった。そこで佐渡は三千石一門の格となって伊勢守邸へと出頭した。この席における佐渡の申立てのいひ廻しやう如何によってはそれこそ御國替えといふ一大事、御家名にも傷がつくことないとも限らねば、この難局に当れる佐渡の胸中察するに餘りありだが、佐渡もさるもの御大老に名の知れたる勢州(阿部伊勢守)がしばしばの御尋ねに淀みもなく一々申し開きたれば、上下眠職を忘れて心を痛めたるこの大事件も、先づさして御家名に障はるやうなこともなく、局を結ぶに至ったのである。事件はここで終局といふことになったのであるが、それに引きかえ不幸にも信濃守殿にはこの江戸御滞在中において病に罹られ、医薬の効も佐渡等の赤誠もその甲斐なくて、そのまま江戸に薨去 されたのである。かくて御遺体には相当の手当てを施し、またも長き道中を盛岡へと送り奉り、聖寿寺に埋葬したのであるが、世に霊承院と申して今に老人等が栄華の夢を語るはこの侯の時代にして、御性行全く佐渡のそれと異ならせ給ひたれば、剛直なる佐渡はしばしば逆鱗に触れて現職を去らねばならぬこと度々あったのである。されど誠忠無二の佐渡は進退のために國より所信を探ぐるやうなことをなさば、常に身を挺んで所謂献身的の覚悟を以て君國のために心血をつくしたのであった。 (五) かくして世は利剛侯の代となったのであるが、御先代豪華を極められたるよりも手伝ひて財政困弊を極め、いろいろと工面もつくして見たなれど、例の繰り延べばかりでもやりきれず、いよいよ御用金といふことになった。そこで東中務などは士族から借上げるといふ議論を唱え、佐渡はこれに反対の意見で、士族を困らして置いては他日事ある場合において御奉公に欠くるところあっても相成るまじとて、迷惑でも一般に御用を承はるといふことにするがよからうと主張し、議論二派に分れ、佐渡は遂に辞して東の意見が行わるゝことになったのである。そこで士族が御用金を承はることになったが、不幸にも佐渡が推測せるごとく、士族の困弊日に甚だしく財政また予期のごとく整理もつかず、江戸勤番の向きなども最早衣食にも窮するといふ場合に陥ったので、更に別案を講じ、鹿角鉱山(尾去沢銅山)を引き当てにて大坂の商人と借入金の交渉を開くことになった。然るにその返済期限を百ヶ年と申出たので、流石の大坂商人もこれはと二の足を踏んだ。今どきなればこそ、九十九ヶ年といふ形式的の期限もあるから、一ヶ年加えて百ヶ年といふまんざら問題にならぬこともなかろうが、当時出し抜けの百ヶ年には大坂商人も喫驚し却って甚だしく信用を失ふた。丁度日本の財政が欧米の金融界に信用を失ふて、外債の応じ手がないと同じ理屈であったのである。或はその財務官のごときものが、山師の網に罹って出来ぬ手数料を貪られて居たと同様の滑稽さもあったのかも知れない。兎も角やぶ蛇の結果を見たのである。ここにおいて佐渡は傍観するに忍びず、自ら起ちて京都に赴き、大に奔走してその信用の恢復に尽力したのである。一体商人相手の財界に立ち入りて、多少の駆け引きの必要もある交渉の局に当たるといふは、佐渡の人格では覚束ない芸当である。今どきでいふならば、待合這入りもせねばなるまい。場合によては心にもなきお世辞も振りまかなければならぬであらうが、彼がごときの人格の佐渡で、果して斯様な任務をやり遂げたであろうか。尤も西洋では日本の桂侯の豪らい軍人とばかり思ふて居ったのに、十五ヶ年の繰り延べを英断したのを聞いて、今更にまた豪らい財界人だと驚いて居るさうだから、同じ軍人気質の佐渡もこの辺の手腕を持って居たのかもしれない。兎も角も目的を達するを得たらしいが、この時であらう、佐渡も時々交際上の必要から一力あたりに出入りしたといふことである。然るに彼は斯様な花柳の街に遊んで居ても、頗る厳格で、かつて下帯を解いたことがなかったといふことである。たしか木戸孝允であったと記憶するが、佐渡を評して今少し砕けた男であったなら、交遊の間に更に得る所ろありたらんにと嘆息したと聞て居る。適評に相違ない。佐渡にはこの注文を容れて貰ひたかったのであるが、彼がごときの人格では到底望むべからずで一得一失已むを得ない。寧ろ危険の欠点を惜まれたのは却ってよい教訓であるのかもしれない。 (六) 佐渡は京都逗留の間、天下の志士にも交際を結んで相往来したことは勿論であるが、折々二条殿へも出入りしたものらしく、彼が持ち前のねばり強い、所謂しぶとい特性は関白殿の前にも遠慮なく発揮せられたものと見えて、二条殿あたりでは佐渡の剛直を称して、南部の鬼佐渡と評判であったとのことである。彼は決して意地悪く妄りに人に当たり散らすやうな男ではない。武士の情けといふことは飽くまでも心得ありて、取り分け下々をあはれむことは、他の同列の左程でもなき類ではなかった。故に深く一般に信服せられたのであるけれども、目上に対しては、所謂威武にも屈せずといふ、苟も道義に外れたことでもあった場合には、堂々と理を辯じて寸歩も後に退かぬ剛直な男なので、しばしば霊承院殿の逆鱗に触れたることあるごとくに、二条殿でもその流儀でやりつけたものと思はる。彼は京都の御用向きも先づ滞りなく辯じ終うせて帰盛の後は、暫く出仕しなかった。顧ふに滞京中四方の志士にも交際して、容易ならぬ天下の形勢はほぼ彼が眼底に映じ来ったので、深く内外のことに憂慮し、如何にこれに処すべきかに就きて苦悶しつつあったのであろう。何分にも当時の状態は敵味方入り乱れて、殆ど渾沌たる有り様であったので、殊には土地東北に僻在して交通の便も欠いて居ったので、事情にはおのづから疎遠ならざるを得ない。真相の如何に那辺にあるかは分りやう筈がなかつたのである。彼は定めて時候後れの情報を得て黒白を分つに苦んで居ったであろう。板垣桑陰はその頃繁く彼が門に出入りして居ったものであるが、桑陰は学者の器量人であるから佐渡は彼を以て國事につきての相談相手となし、議論を上下したものと思はれる。果たせるかな佐渡は遂に桑陰を伴ふて京都に赴くこととなった。天下の政論はいよいよ極端に沸騰して、勤王佐幕の過激の徒は至る所に衝突し、血生臭き騒動は号外発行の遑もなく、二号活字満載といふ有り様であったのだ(当時新聞といふものがあったらばだ)。最早時勢はいよいよ切迫して藩論一決何でも方向取り極めねばならぬハメに到着したのである。議員選挙の前夜のごときものではない。無論運動費を誤魔化すやうな芸当の行はれる余裕もない。奥羽同盟佐幕といふことに連判したのである。無論異議者のない訳ではなかった。現に中嶋源蔵割腹といふ悲劇も演ぜられた。奸臣殺忠臣といふ血書などは、将に各社荒ふて写真に撮り、新聞に刷り込む好材料であったのだ。兎も角も奥羽の同盟が出来た。委曲の事情は京都の佐渡へも報告の必要があるといふので、野田廉平使者の役を承はり、京都を指して盛岡を出発したのである。 (七) 時局に対する南部藩の態度、前述のごとくに決定した次第は、南部家の重な御親戚にして且つ特別に親善の間柄たる加州侯に申し通す必要もあったものと見え、廉平は京都への道すがら、北陸道を金沢へと迂回して加州家を訪問し、侯に拝謁を請ふて藩論佐幕といふに一決し、既に奥羽同盟にも連判したる次第を具に言上におよび、かくして侯の御意見如何にと伺ひ出でたるに、侯は以ての外に打ち驚かれ、藩の方向の尚ほ取り極まる以前ともあらば御相談に応じて意見申し陳すべきこともありたらんなれど、最早藩論一致して奥羽の同盟にも連判をしたとある以上は、所謂十日の菊で、唯だ事の次第を承り置くの外、意見を申し述ぶべき余地なきに候はずや、惜しいことをしたものだと、喜ばれぬ言葉の外には佐幕などとは然るべからず、よろしく勤王たるべかりしものをとお顔色に読みたれば、廉平もこの場においてはいたく面目を失ひその座にもたえがたくてほとほと困じはてたれど、たとひ加州侯の御意見なればとて、今更に立ち帰って評定の仕直しも出来べき訳のものならねば、手持ち無沙汰の体に侯が藩邸を辞し草にも木にも気を置かるる心して忍び忍びで漸く京都へと辿り着き、やがて佐渡が旅館を叩きて、密かに國許における評定の顛末を事細やかに佐渡に告げ、斯く國論一致して奥羽の同盟にも連判したる以上には、一時も早く帰国して采配を取らるべしと、かねて仰せ含められたる旨をも伝えたのである。静かに始終を聞き取りたる佐渡は、あらたまる態度もて、お國許においての御評定仰せのごとくに既に國論一致したりとある以上は、致し方も候はず、佐渡も所存の臍を固めて唯だ命のままに従ひ申すべしと、ここに明確に時局に対して進退を決定したのである。この佐渡が進退を処決した当時の様子から考へ見れば、彼は強も最初から佐幕党ではなく、コトによったら國論のここに決定したのを本意なく感じ居ったのかも知れない。國論一致とある以上は致し方がなしといふ彼の一言は、充分に考え見るべき価値があるのだ。自動的ではなくて他から余儀なくされたとも見られない訳ではない。丁度西郷南州翁が私学校党に要せられて、彼がごとくに余儀なくなったのと同じやうにも見られる。然し乍ら、古来英雄といふいたづらものは、内々おそろしい大事をたくらんで居ながらなかなかに本音を吐かず、故意と心にもないあべこべな人の反動を惹き起こしさうな言辞を弄してあほりたてたりたきつけたり、さうしていよいよ熟して目的通りの沸騰点に至るをまって、巧みにこれを利用するといふ悪い癖がある。佐渡もまたこの筆法を学んだのではあるまいか。 【参考】きろく解読館 人物志 楢山佐渡 えいぞう館 楢山佐渡隆吉 > 楢山家略系 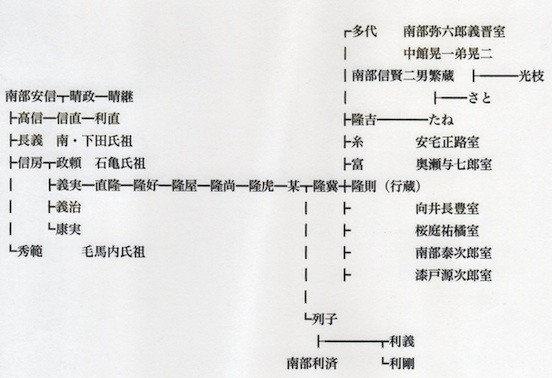 |